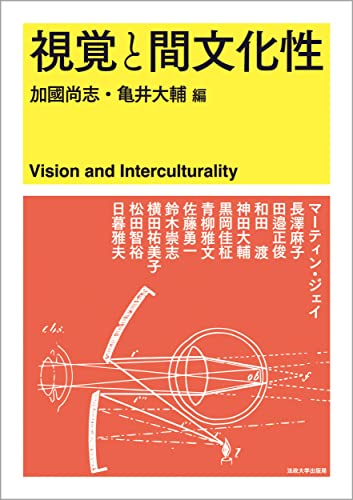本書は、現代思想の代表的人物の一人であるミシェル・フーコーの思索を、「一九七〇年代後半から八〇年代前半の「後期」と呼ばれる時期を中心に」(5)論じている。なぜ「後期」に注目するのか。それは、この時期に展開されたフーコーの思想は、「理論的かつ実践的に捉えられた現在の社会のありようにたいして、主体がいかに関わるのかという問いを改めて提起するものとてしても読むことができる」(9)からだ。
注目すべきは「拒否」という態度である。「はじめに」で著者は次のように述べる。
社会が大きく動きとき、そのきっかけはしばしば、人びとが何かを積極的にしないこと、いつも当たり前のようにして行われていることを拒むことにある。広場革命にも気候ストライキにもそうした側面がある。この「拒否」という態度の力強さは、誰もがある程度はわかっているが積極的に目を向けようとはしないことについて、それはおかしいと言い切り、否を突きつけるところにある。そうした振る舞いは、それまで当たり前だと思われていたこの世界の日常から自明性を剥ぎ取るからだ。(3)
世界の日常からの自明性の剥ぎ取り、つまり「いま現在ここにあるものがこれまでもあったし、これからもあるだろという思い込みからみずからを断ち切るという決断」(95)が、歴史を変容させる大きな流れとなる。
政治経済的な要因では説明しきれない何かが起きるとき、その原動力となるのが、フーコーの統治論からすれば、このようには統治されたくないという耐えがたさと拒否の意志であり、みずからがいまという固有な時のただなかにいるという、ここから先はみずからの選択によって変わりうるという、モダンな-時代区分としての「近代」には限られない「いま」についての-感覚なのである。(95)
現代の統治において、「このように統治されたくないという耐えがたさ」を抱いている人は少なくないだろう。本書はフーコーの統治論を通じて、そのような人たちに対して、「このようには統治されない」ための手がかり、自己と社会の新たな姿を構想する手がかりを与えてくれる。「私たちには、対抗導きの可能性はつねにすでに備わっている」(96)のであり、フーコーが示したように、しかしフーコーとは別のやり方で実践することが可能なのだ。