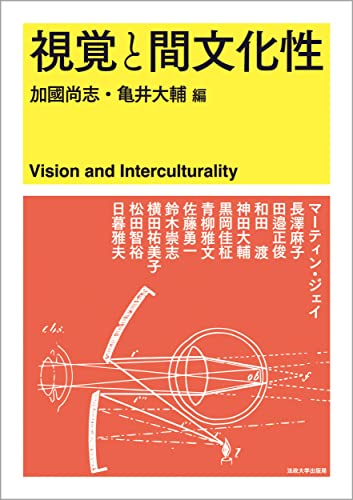本書『視覚と間文化性』は、1993年に出版され、2017年に日本語に翻訳された著作、マーティン・ジェイ『うつむく眼-二〇世紀フランス思想における視覚の失墜』に対して、「日本からの応答をなすもの」(4)である。『うつむく眼』で描かれた思想史からは見えてこない、視覚を巡る思想史が各論者により展開され、「「新たな」ことがらを現れさせる可能性」*1を持った刺激的な内容となっている。
まずは、マーティン・ジェイ「融合する地平?-日本における『うつむく眼』」を読むのがよいだろう。『うつむく眼』が引き起こした反響や、日本特有の視覚体制について論じている。これらの議論を通じて、「視覚性」に対するジェイの問題意識を理解することができ、その他の論考を理解する手助けとなるだろう。
以降は各章を収録順どおりに読み進めてもよいが、『うつむく眼』以降の30年間のフランス現代思想を知るうえでも、編者の一人である加國尚志氏の「メルロ=ポンティの知覚論-マーティン・ジェイ『うつむく眼』の周囲で」が参考になる。加國氏は、ジャック・ランシエールやジョルジュ・ディディ=ユベルマンらの「イメージ」論から、「二〇世紀のフランス思想において、「イメージ」の概念が「失墜した」とは簡単には言えないように思われる」(195)として、次のように述べる。
私たちの眼は、うつむいたままではなく、ときには見上げたり、まばたきを繰り返したりしながら、あふれかえるイメージの中をさまよい、そこに欠けているイメージを求め、そのイメージが、それ自身を見せながら何かを「見えるようにする」ことを待っているのである。(200)
『視覚と間文化性』に通底しているのは、視覚に対するこのような「ゆらぎ」や「両義性」である。例えば、もう一人の編者である亀井大輔氏は、デリダの視覚に対する両義的な特徴を踏まえ、「絶対的に不可視なものとは、視覚を可能にするものであると同時に、視覚を他なるものへと開き、諸感覚どうしの代補的関係を打ち立てるものである」(302)と指摘している。
そして、本書のタイトルにもある「間文化性」に着目しつつ、視覚と触覚との関係について論じているのが、横田祐美子「空気に触れる眼-イリガライと触覚的視覚」である。本論文は、楳図かずおの作品や美術展、眼圧検査といった身近なものにも根ざしつつ視覚文化を解きほぐしており、哲学や思想に詳しくない読者にとっての導入にもなるだろう。また、次の言葉からは、「女性的なもの」に対する横田氏の意気込みを感じ取ることができる。
空気は、水は、女性的なものは、そこにあるだけでその存在に気づかれることがほとんどない。ひとびとを触覚へと立ち返らせるためには、壁を通り抜けるほど強く吹くことが、容器から溢れ出すことが、ときには必要となってくる。それはいわば女性的なものが吹き荒れる反乱であり、氾濫だ。(262)
また、SNSの視覚体制やバンクシーの作品・活動について分析している、日暮雅夫「視覚と新自由主義」も、視覚文化を理解する導入としてよいだろう。現代社会での過剰に可視化されていく状況に対して危機感を覚える一方で、「「見えないもの」とされていた人々や社会問題を「見えるもの」としようとする」(328)試みは、引き続き必要とされているのだ。
モーリス・メルロ=ポンティは、「哲学をたたえて」において、「哲学者が哲学者として認められるのは、<明証性>にたいする眼と、<両義性>にたいする感覚とを不可分に合わせもつことによってです」*2と語っていた。「視覚」はまさにこの「両義性」という性格を有するものでもあり、それ故に本書に収録された各論文の記述方法や各論者の思考方法もまた両義的であることを避けられないだろう。そして、これらの視覚文化論を通じて見えてくるのは、「両義性」という人間の条件である。「視覚」というテーマ以上の広い射程を持った一冊である。